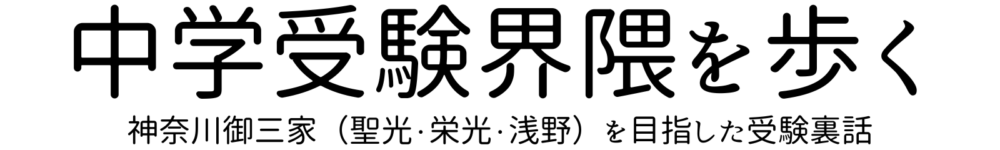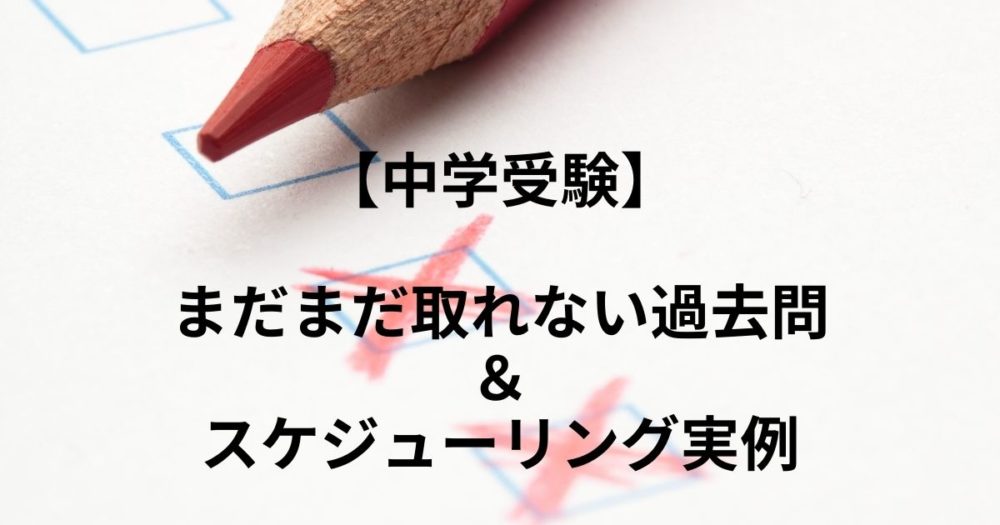10月になりましたね。9月から始めた過去問、まだまだ解けなくてどうしようと思ってたりしませんか?
やり始めたのはいいけど、1か月たってもなかなか得点率上がってこないし、くだらない間違いはするし、これ本番大丈夫なんだろうかと一番苦しかった時期な気がします。
・このころにどのくらい取れてたらいいの?
・こんなに取れなくてどうにかなるの?
・どの志望校から優先的に解く?
こんなことを考えているパパママさんへ、当時のわが家の様子を振り返ってみます。
うちだけ出来ないんじゃ?
って思っていませんか?そんなことないです。
今日、1年前の先輩ママ友とのラインを振り返っていたら、私、叫んでました。

合格最低点まで50点も足りないんだけど!(4科で)
そんな状況でした。
今回は10月頃の過去問の取り組み方、実際の受験校の過去問状況を教科別にまとめてみますね!
過去問の取れ方状況(算数)
過去問の状況
うちに限ったことなのかどうかわかりませんが、年度によって取れる取れないにばらつきがありました。特に算数。
栄光
特に栄光の算数は問題がかなりの難度。思考系中の思考系、サピックスでいうBタイプです。
徐々にできるようになってくるというよりは、問題によって取れたり取れなかったり…。鉄板の子たちは安定して取れるのでしょうが、鉄板になり切れないわが子。全く安定しませんでした。
本人も、
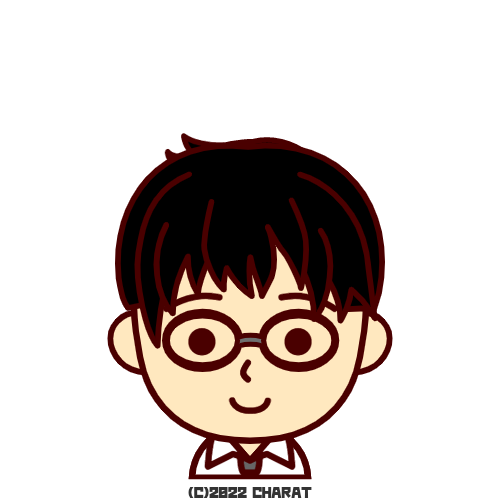
算数は出てくる問題との相性次第だった
と。うちの子にとっては、解法が思いつく問題と、思いつかない問題の差が一番激しかったのが栄光でした。
栄光の場合は問題数が少ないので1問あたりの配点が大きいと言うのも厳しいところですね。
浅野
浅野の算数は、これまた栄光と全く違うタイプ。いわゆるサピックスでいうAタイプ(典型問題)ですね。問題数が多く、奇をてらった問題がないので、とにかく早く正確に解くことが求められる問題でした。
これもまた、ケアレスしまくりのわが子。なかなか点が取れず。もうどっちもダメじゃん!です。間違いで多かったのは
・くだらない計算間違い
・最後の計算(例えば最後の÷2など)を忘れる
・自分の書いた字が汚くて間違える
・わからない問題にこだわりすぎる
あるあるかもですが、これにつきます。7-3=2みたいな意味の分からないことを平気でやらかしてきます。「は?!」です。こればっかりはいくら演習したって意味がない。一番困りました。
とにかく、落ち着いて問題に向かうこと。大問1の計算問題は必ず取り切ること。右手の親指の付け根に赤ペンで丸点を書いて、これ見たら落ち着くことを思い出して!ということもしました。

塾経営をしていた父によると、大問1の(1)というのはまだ問題に頭が入り切れていないので、一番間違いやすい!注意すること、だそうで、これは気を付けてました。
逗子開成
逗子開成の問題も奇をてらったものはなくて、解きやすかったようです。偏差値55の壁=55を超えると問題の質がぐっと上がる、と聞いていましたが、我が子の様子を見ていても、逗子開成と浅野の問題の取れ方はだいぶ違いました。
オープンキャンパス時に在校生から聞いた「基礎を忠実に」という問題だと本人も落ち着いて解けていたようです。ただ、鎌学の算数を解いたときにてこずっていた問題があったので、もしかしたら逗子開成の問題と相性がよかったのもあったかもしれません。
過去問は目標点数を決めて分析
わが子は算数が苦手だったのもあり、
栄光は40点/70点満点を目指して。その他の学校はせめて受験者平均を取ろう!
というのが目標でした。国語得意男子だったので、算数と国語でプラスマイナスゼロを目指せば何とかなるかも!と。社会と理科が比較的安定していたのも大きかったです。
過去問を解いた後は、
・目標点数まで何点足りないか。
・どの問題を取ればその点数に達するか
・取れそうな問題を取り切っても目標点に達しない場合はあきらめて他の教科でカバーを狙う
こんな綱渡り的なことでいいのか?!と思ったりしますが、我が子にはこれが最大限のやり方だったと思います。

この問題が取れてたら平均点行ったね!という具体的な数字がみえたので、できないなりにも楽しさはあったようです。
10月の今できることは
10月に入りできることは
・志望校特訓の問題をしっかり復習して定着させる
・過去問を解き、分析を含めた見直しをする(見直しの方が時間かかります)
・基礎問題を(サピックスの基礎トレのような)おざなりにしない
息抜きには、
・読書
・時間を決めてゲーム
・たまの外食
をしてました。

10月はコロナワクチン接種の副反応がひどくて、数日間ロスしてしまいました…。
模試としては半ばにマンスリー、次の週末に志望校別SOもあった10月なので、知識の定着もしっかり意識した月でした。
10月に解いた過去問と得点率
過去問のスピードとしては、1週間に1校1年分(4科目)と聞いていたので、それを目安に解いていました。得点率めっちゃ悪くて恥ずかしいですが、皆さんの参考になればと意を決して公開します。
10月の記録を見ると、算数は
| 日付 | 学校名/年度 | 得点率 |
| 10/12 | 栄光2017 | 22% |
| 10/16 | 栄光2016 | 37% |
| 10/27 | 逗子開成2020 | 79% |
| 10/31 | 栄光2015 | 54% |
本来であれば、一度に4教科解くのが理想なのでしょうが、なかなかまとまった時間を捻出するのが難しかったので、わが家はそこにはこだわりませんでした。とにかく隙間時間に過去問を解いていった感じです。
順序としては最新の2021年度のものを残して、2020年以降、新しいものから古いものへ解いていきました。
9月の詳しい過去問状況は、また改めて載せますね。
過去問の優先順位
過去問を解いていく順番ですが、第一志望は10年分なので、必然的にそちらの優先度は上がります。ただ、栄光とその他の学校の傾向が全く違うので、勘が鈍らないように栄光はまんべんなく解くように心がけました。
第一志望10年分・第二志望5年分・第三志望3年分
と言われて、それに沿って進めましたが、浅野は心配だったのでもう1年付け足しました。
ざっとまとめてみると
9月は栄光×2、 浅野×3、逗子×1
10月は栄光×3、逗子×1
11月は栄光×2、浅野×2
12月は栄光×2、浅野×1、逗子×1
大体目安通りに一週間1校分解けてたかなと思います。これを見ると9月はまだちょっと余裕があったかな。
このスケジューリングで、課題になっていた年数分はすべて解き終えることができました。
10月は一番しんどい時期
今回は
・どのくらい取れてたらいいの?
・こんなに取れなくてどうにかなるの?
・どの志望校から優先的に解く?
と思っている受験生のパパママさんに。算数に絞って、わが家の10月の過去問状況をまとめてみました。どのくらいとれていたらいいのかということについては、親としては本当に知りたいところですよね。
でも振り返ってみると正解はほんとうに個人個人それぞれなので、断言はできません。

わが家の状況、受験生の一例ということでUPしてみました。
9月から10月は過去問も取れないし、塾と模試、特訓や過去問でかなりいっぱいいっぱいな時期ですね。一番しんどい時期と言っても過言ではないと思います。
過去問、まだ取れない時期です。過去問の受験者平均、合格者平均は4か月先の受験生が取った点数です。とにかく今は焦らずやるべきこと、問題の取捨選択、優先順位を決めて無理せず勉強を続けていってくださいね。
では、別の教科についてはまた記事にしますね!