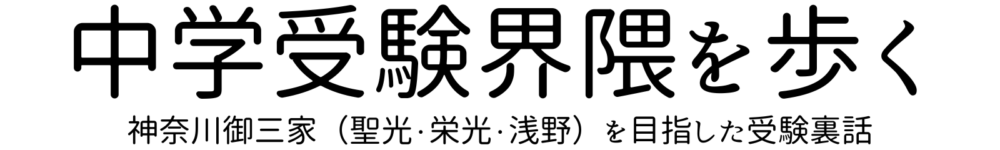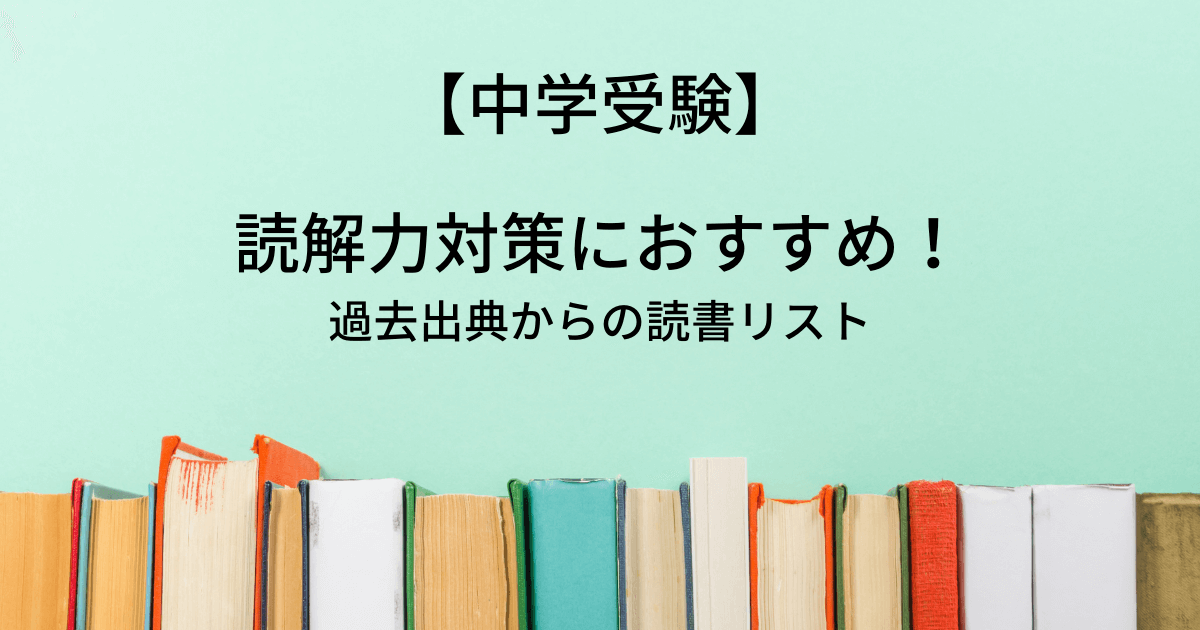読解力を伸ばすにはどうしたらいいですか?
お子さんの読解力に悩んでる方、かなり多いですよね?
ほんとに国語の対策には皆さん苦労されてますよね。
私も何度か相談を受けて色々アドバイスをさせていただいたこともあるのですが、読解のテクニック的なことは塾で教わると思うので、今回は読んだ本のリストを参考までにUPしようと思います。
どんな本を読めばいいの?
子供に本を読ませたいけど、どんな本がいいの?と思われている方、本の選び方としては
塾教材に出てきていたり、入試でよく取り上げられている文章・作家
をお勧めします。
塾のテキストや入試問題に取り上げられている文章には、必ず出典が書いてありますよね?
出題の文章は一部分なので、その文章を丸ごと1冊買ったり、入試問題に良く取り上げられている作家さんの新旧作品を買ってみることをお勧めします。
出題に取り上げられている文章というのは、出題者がお子さんたちに考えてほしいテーマ、読み取ってほしい主人公の気持ちなどが書かれているので、小学生が読むにふさわしい文章になっています。
子供に読ませた本を私もほとんど読みましたが、大人が読んでも、嫌みがなくスムーズに心に入ってくるものが多く、感動したり勉強になったり学びがある本がほとんどだったように思います。
受験勉強の合間に読む本ですから、効率よく良書に出会う必要がありますよね。ぜひ、出典から選んでみてください。
読書の効果
読書リストをUPする前に、読書の効果についてわが子を例にして少し書きますね。
わが子はほとんど本を読まない子でした。
読書をしてほしくて短編集などをそれとなく置いておいてもスルー。少しずつ読み始めたのは3年生の後半ごろでしょうか。それまでは図鑑すら開かない子でした。
3年生の9月から塾通いを始めましたが、記述は苦手で解答欄は真っ白か1行。
まだ3年生だったのでそこまで焦りはありませんでしたが、書けるようになるのだろうか…という不安はありました。
4年生1年間も以前よりも読書量は増えましたが、目立ったような変化もなく、記述もちょっとずつ書けてきた…??程度。
それが、5,6年生になると、塾でのテキストの量が増えたせいもあるのか本を読むスピードが格段に速くなり、その分読書量が増加。
それにともなって6年生後半の特訓が始まるころになると、記述問題で先生に褒められることも増え、白紙だった記述が得意分野になりました。
もちろん、読書をあまりしなくても記述問題を得意としているお子さんはたくさんいらっしゃると思います。
が、わが家の場合は読書量が増えるとともに、記述力が上がり、国語の成績も安定したので、読書と国語力は関係ないとは言い切れないんじゃないかな、と思ってます。
読書リスト
さて、その息子が読んできた本がこちらです。
| 書籍名 | 著者名 |
|---|---|
| 十四歳日和 | 水野瑠見 |
| ぼくのとなりにきみ | 小嶋 陽太郎 |
| リマトゥジュリマトゥジュトゥジュ | こまつあやこ |
| キャプテンマークと銭湯と | 佐藤いつ子 |
| 奮闘するたすく | まはら三桃 |
| あと少し、もう少し | 瀬尾まいこ |
| その扉をたたく音 | 瀬尾まいこ |
| そしてバトンは渡された | 瀬尾まいこ |
| 海の見える理髪店 | 萩原浩 |
| 西の魔女が死んだ | 梨木香歩 |
| 宇宙への秘密の鍵 | スティーブン・ホーキング |
| あしたの幸福 | いとうみく |
| 朔と新 | いとうみく |
| 52ヘルツのクジラたち | 町田そのこ |
| 雪のなまえ | 村山由佳 |
| もどかしいほど静かなオルゴール店 | 瀧羽麻子 |
| 雑草はなぜそこに生えているのか | 稲垣栄洋 |
| たたかう植物 | 稲垣栄洋 |
| 目の見えない人は世界をどう見ているのか | 伊藤亜紗 |
| 水を縫う | 寺地はるな |
| ガラスの海を渡る舟 | 寺地はるな |
| 声の在りか | 寺地はるな |
| ヨンケイ | 天沢夏月 |
| みかづき | 森絵都 |
| ツナグ | 辻村深月 |
| 琥珀の夏 | 辻村深月 |
| むこう岸 | 安田夏菜 |
| ミツバチと少年 | 村上しいこ |
| 羊と鋼の森 | 宮下奈都 |
| つぼみ | 宮下奈都 |
| ぼくは朝日 | 朝倉かすみ |
| 金の角を持つ子どもたち | 藤岡陽子 |
| with you | 濱野京子 |
これ以外にも、ミステリーや推理もの(東野圭吾や太田愛など)を読んでいることもありましたが、今回はそちらは省かせていただきました。
こちらで記録として残してあるもののみなので、またもし読んだ履歴が見つかれば追記いたします。
また、今年も新しい本がどんどん出てくると思いますので、新刊チェックをして読んでみるとよいと思います。出題は結構新しい作品から出ます。私も今年注目の本をリサーチしてまた記事にしますね。
できるなら親子で会話を
本を読み終わったら、親子で感想を言い合うのもとても有効でした。
私も子供が読んだ本はすべて読みましたが、読後に感想を言い合うと、子供が読み取れてなかったところを補えたり、思ったことを言葉にする練習にもなりました。
私と息子の感想が似ていて、「あの主人公の行動は腑に落ちないねー」とか、「いまいち最後がもやもやしたよねー」と意見が合い、「やっぱり親子ー」と思ったりもして楽しかったです。
親子のコミュニケーションにも、お勧めします。
まとめ
今回は、受験期に私たちが読んできた本をご紹介しました。
読解力が絶対上がるかと言えば、個人差があるので言い切れません。ただ、わが家の場合は読書が考え方や意見を持つことに大きく役立ってくれたのは事実です。

どんな本を読んだらいいんだろう・・・
と悩まれている方のお役に立てれば嬉しいです。
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。